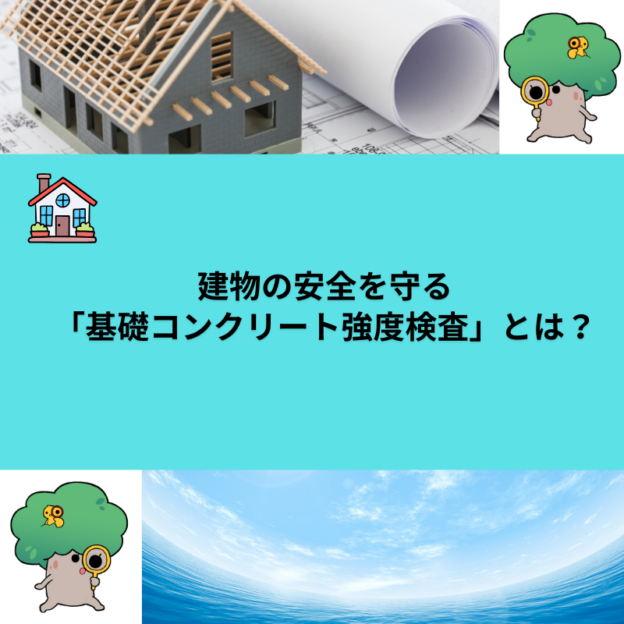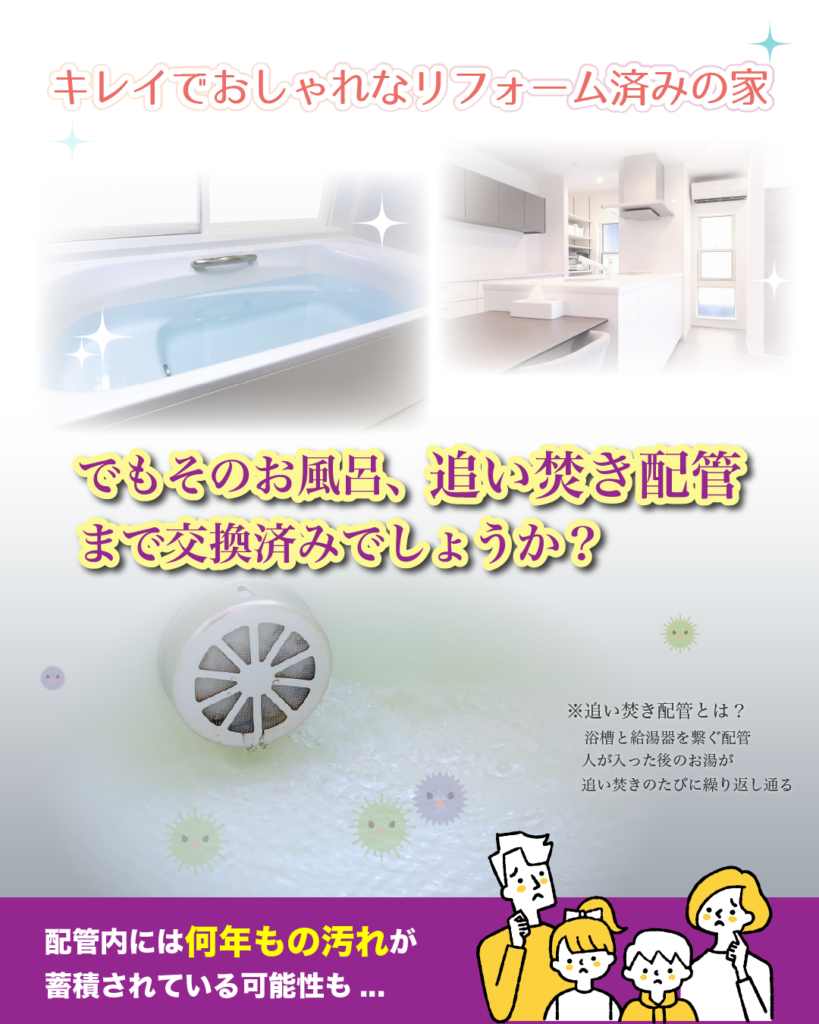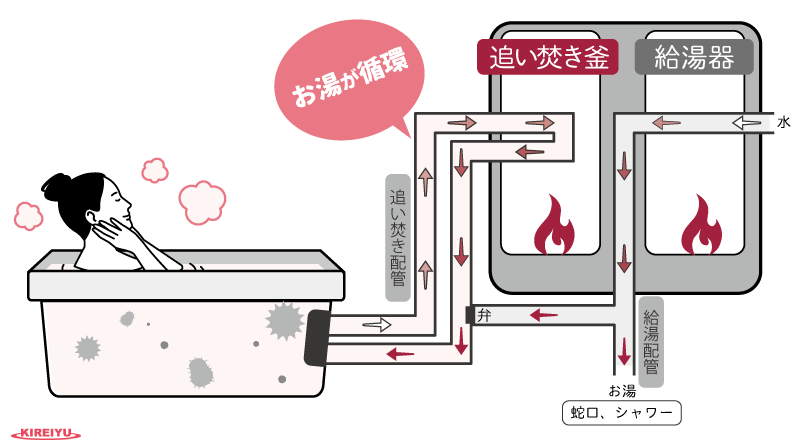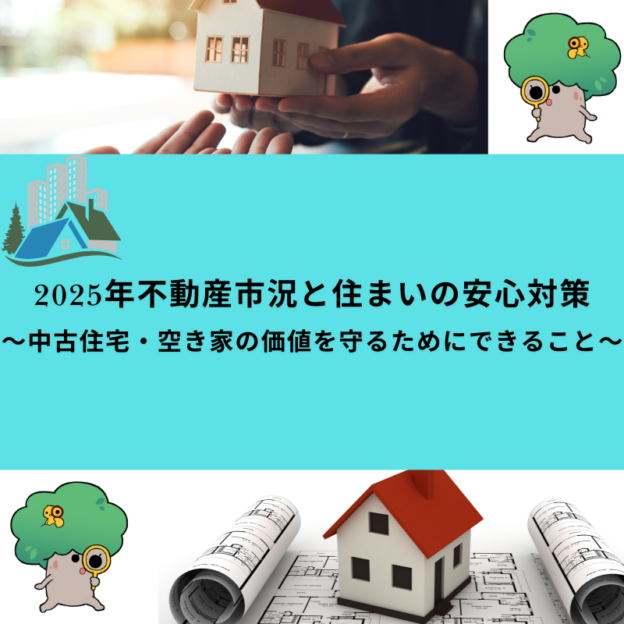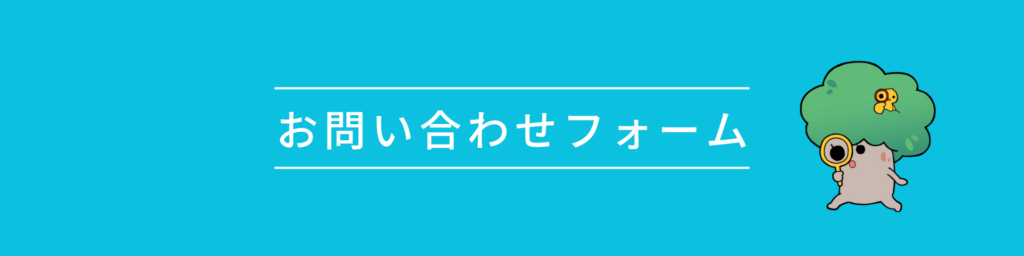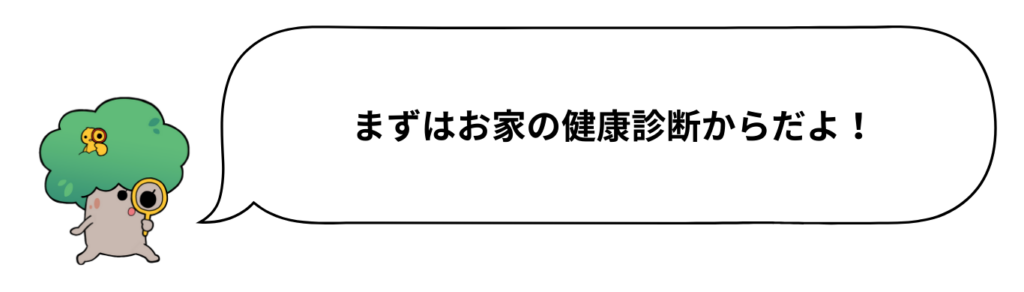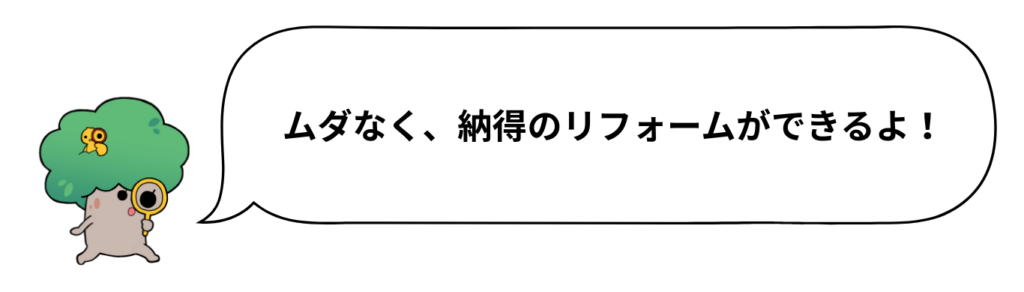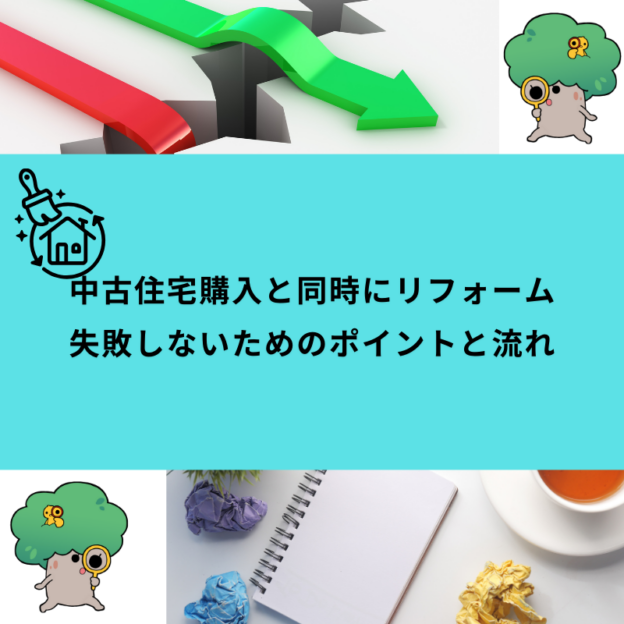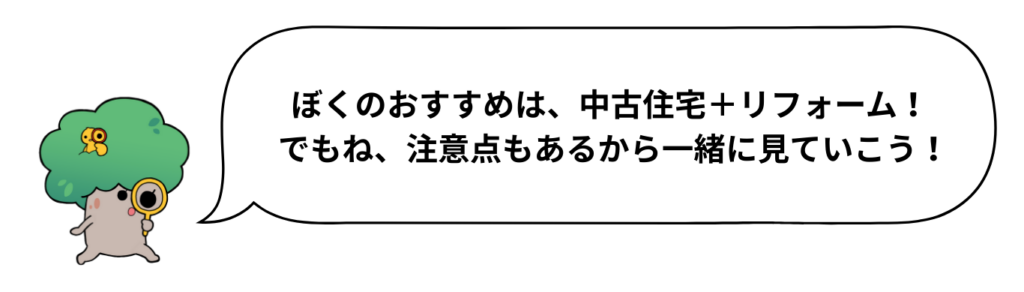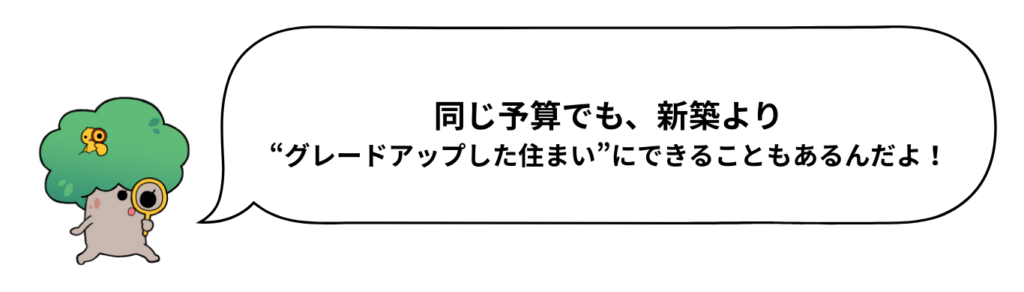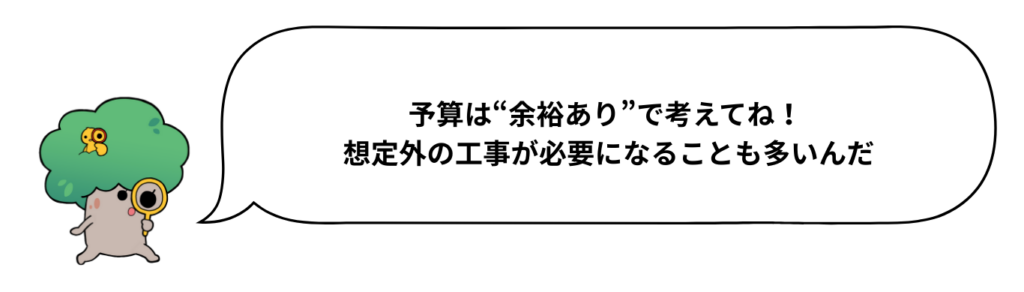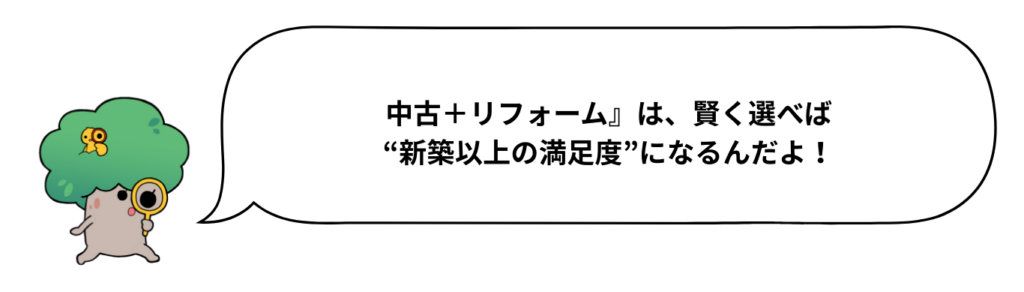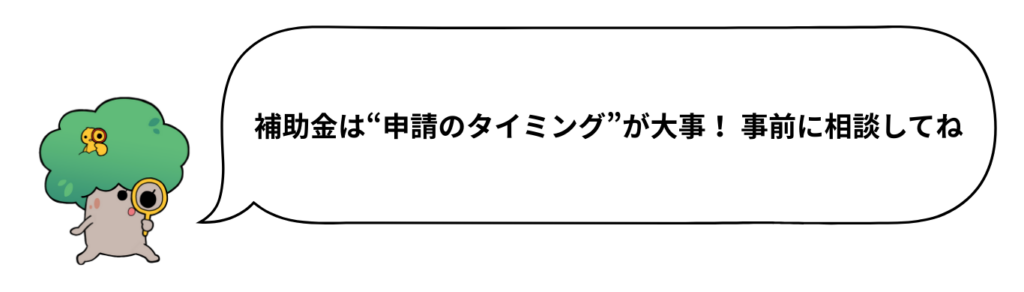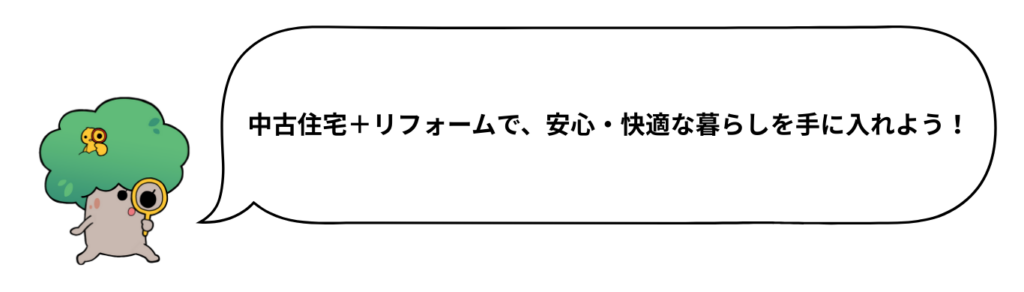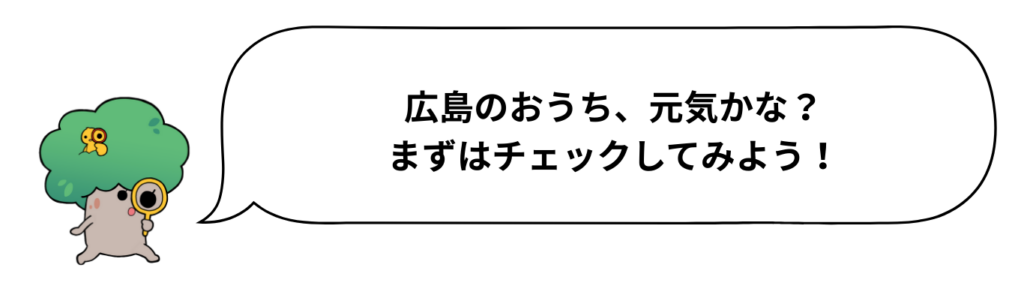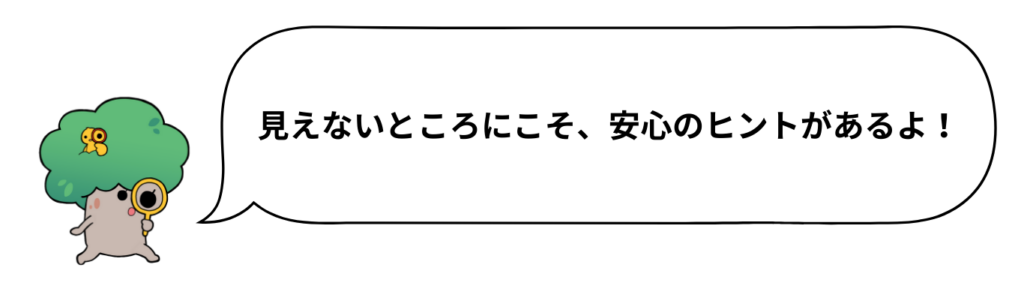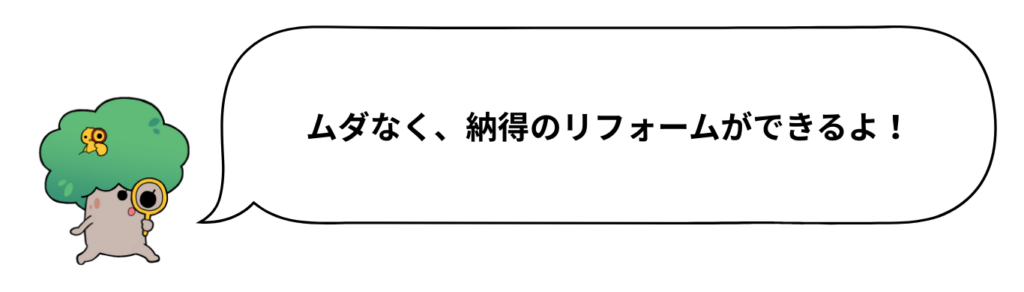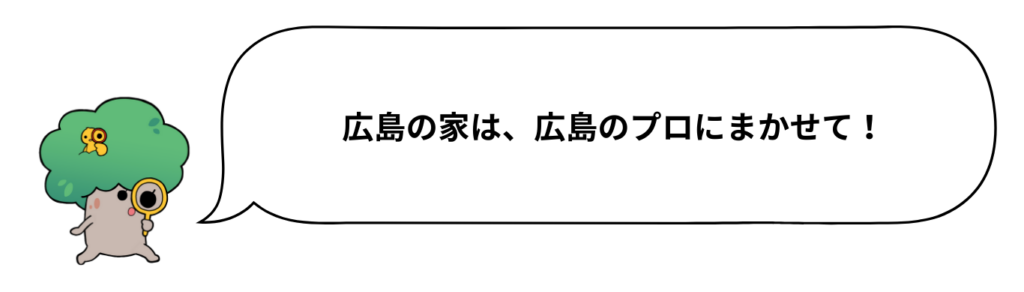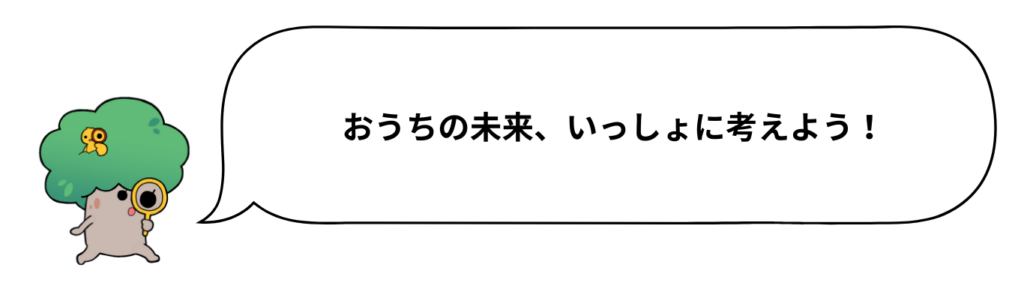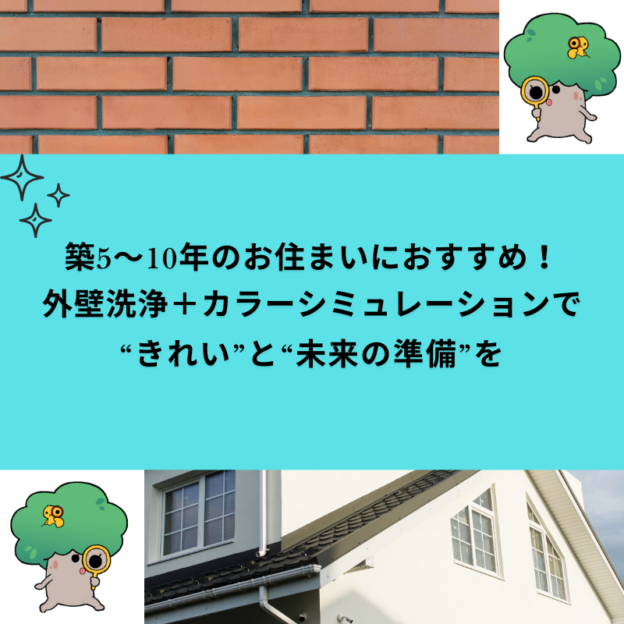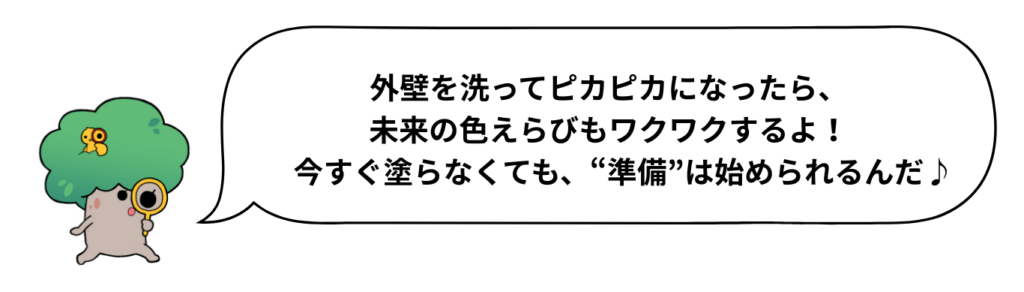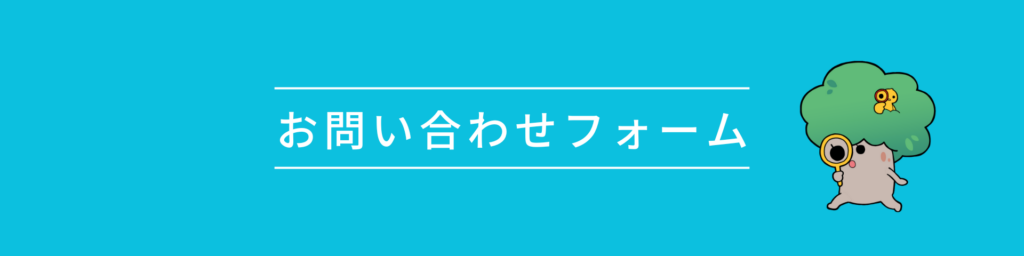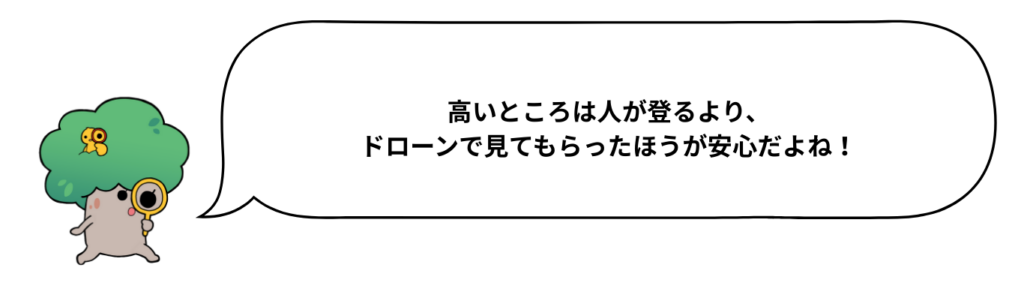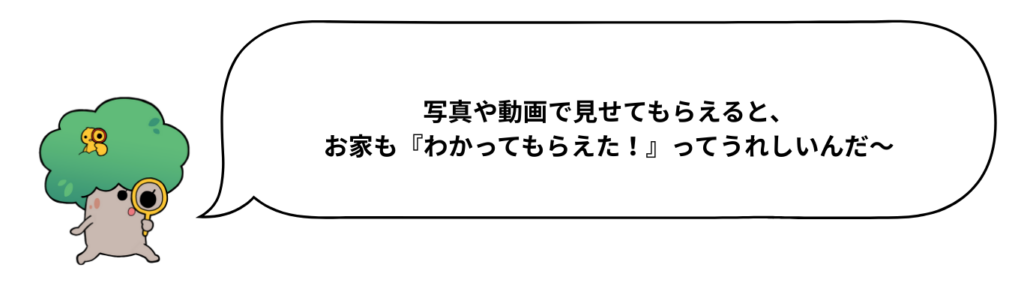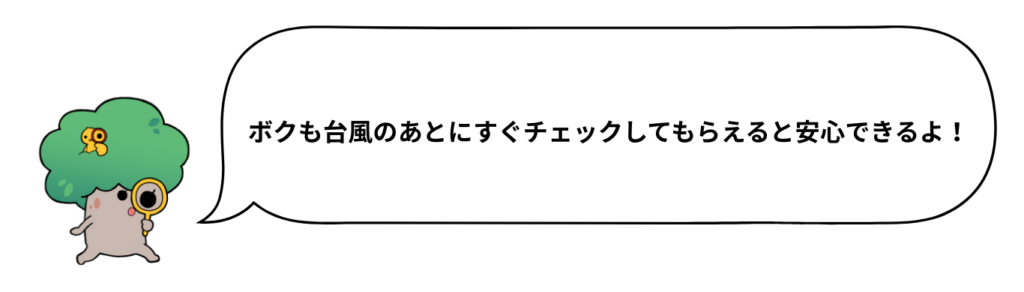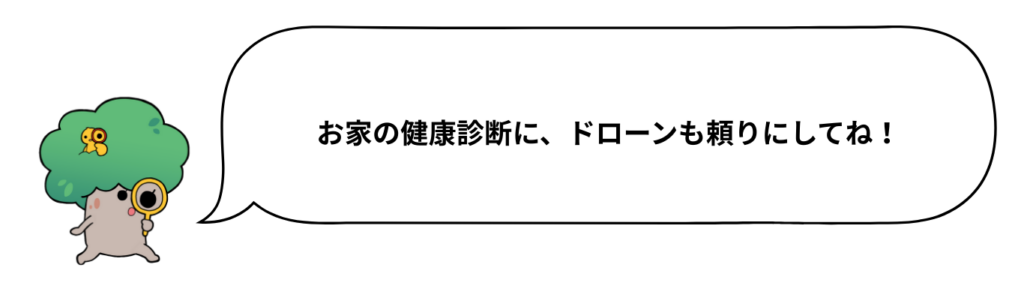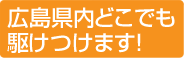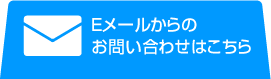「その音、ほとんどが“住宅が発するサイン”かもしれません。」
「誰もいないのにパキッ」「天井からコツコツ…」
そんな不安を感じるご相談は意外と多く、心霊現象と思い込んでしまう方も少なくありません。
しかし実際は 家そのものの変化や、害獣・湿気などの“物理的な原因” であることがほとんどです。
住宅内の音の正体は?考えられる主な原因
「音の多くは“家鳴り”や“動物の侵入”が原因です。」
・家鳴り
が温度・湿度の変化で伸縮し、「パキッ」「ミシッ」と鳴る現象。
特に木造住宅では日常的です。
・動物の足音
ネズミ・イタチ・ハクビシンなどが天井裏を走ると「ドタドタ」「カサカサ」と聞こえます。
・外部要因
風圧、排水音、隣家の生活音が響く場合もあります。
住宅内の音の正体とは?
住宅内で聞こえる音の正体は、主に以下のようなものがあります。
1. 家鳴り:木材や金属が温度変化に反応して発生する音です。
2. 動物の足音:天井裏や壁の中に住み着いた動物が原因となることがあります。
3. 外部の音:近隣の交通音や風の音なども影響します。
これらの音は、心霊現象と誤解されることもありますが、実際には物理的な原因が多いのです。

心霊現象と家鳴りの関係
心霊現象と家鳴りは、しばしば混同されることがあります。
家鳴りは、物理的な要因によって発生する音であり、特に古い家や木造住宅でよく見られます。
一方、心霊現象は、目に見えない存在が関与しているとされる音です。
このため、家鳴りの音が心霊現象と誤解されることが多いのですが、実際には多くの場合、物理的な原因が存在します。
ホームインスペクションに必要な調査項目
家鳴りや外部の音が気になる場合は、以下の項目を確認することが重要です。
- 温度・湿度の測定:これにより、家鳴りの原因を特定できます。
- 建材の状態:老朽化や劣化が音の原因となることがあります。
- 周囲の環境:近隣の音源や交通量も影響します。
家鳴りと温度・湿度の関連性
家鳴りは、温度や湿度の変化と密接に関連しています。
特に、木材は湿度の影響を受けやすく、湿度が高いと膨張し、低いと収縮します。
このため、季節の変わり目や天候の変化に伴い、家鳴りが発生することがあります。
また、温度差が大きい場合も、音が発生しやすくなります。
これらの要因を理解することで、音の原因を特定しやすくなります。
一戸建てとマンションの違い
一戸建てとマンションでは、音の発生源やその感じ方が異なります。
一戸建てでは、家鳴りや外部の音が直接影響しますが、マンションでは隣接する住戸からの音が気になることが多いです。
また、マンションは防音対策が施されていることが多いですが、古い物件では音漏れが発生することもあります。
このため、物件選びの際には、音の問題を考慮することが重要です。
音の発生源を特定するための対策
音の発生源を特定するためには、いくつかの対策が有効です。
1. 音の記録:気になる音を録音し、時間帯や発生状況を記録します。
2. 専門家の相談:音響の専門家に相談し、音の原因を特定してもらいます。
3. 住宅検査:専門の業者による住宅検査を行い、物理的な原因を調査します。
これらの対策を講じることで、音の問題を解決しやすくなります。
音の問題を解決するためのリフォーム
音の問題を解決するためには、リフォームが有効な手段となります。
特に、防音対策や建材の選び方を見直すことで、音の伝わり方を改善することができます。
リフォームを行う際には、専門家の意見を参考にしながら、効果的な対策を講じることが重要です。
これにより、快適な住環境を手に入れることができます。