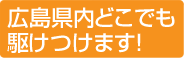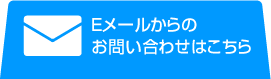2025年2月26日(水)
先週は非常に寒い1週間でしたね。
これだけ寒い日が続くと、お客様もなかなか玄関を開けたくなくなり弊社社のサービスについても
『もう少し暖かくなってから・・・』
とお断りされるケースも増加してきます。
しかし週間天気予報を見ると今週からは気温がグッと上がってきます。
床下点検や建物インスペクションの依頼もそろそろ増加してきますので社員一同、気を引き締めて業務に尽力してまいります。
さて、弊社では、防蟻処理施工から一定の年数が経過した際にアフターサービスの一環として床下定期点検をご案内させていただいています。
その中で一番、多い質問が
『床下ってどこから入るの?』です。
そこで今日は、床下点検はどこから実施するのか説明致します
1.床下点検口より


2.和室のタタミ下より

上記のどちらかを使って床下に入り込む事が多いです。
お客様にお願いしておきたい準備としては、和室のタタミから入る場合は、タタミの上ノカーペットや荷物をあらかじめ移動しておいていただくと非常に助かります。
点検口を収納庫として、ご使用されている場合は、収納庫の中身をあらかじめ出しておいていただくと作業が短時間ですみますので助かります。
何度もお伝えしてきていますが、床下は普段の生活上、なかなか点検できない部分なので、定期点検のご案内が届いた時は必ず点検を受けていただき、大きな劣化事象にならないうちにメンテナンスをして建物の維持管理を実施していきましょう!