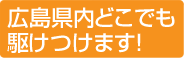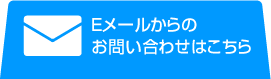中古住宅や既存住宅のインスペクション( 建物状況調査 )を行っていると、「床の傾き」や「沈み」による不具合をよく目にします。
今回は、広島の住宅で実際にあった調査事例をもとに、デジタル水平器を使って床の傾きを確認した結果や、建物の間取りが傾きに与える影響についても解説します。
◆ 傾きの基準とは?
床や建物が傾いているかどうかを判断するには、“どの程度の傾きが許容範囲か”を知っておくことが重要です。
一般的な目安としては、以下のようにされています:
- 3/1000(3mm/m)以上の傾き:人が体感する可能性あり
- 6/1000(6mm/m)以上の傾き:実生活に支障が出る可能性あり
- 10/1000(10mm/m)以上の傾き:建物の不同沈下を疑うレベル
つまり、1mの距離で6mm以上の高さ差があれば「傾いている」と判断されやすい基準となります。
◆傾きとは?
わかりやすく言うと…
もしお部屋の床にビー玉を置いたらどうなるか想像してみてください。
- まったく動かなければ問題なし(~3mm/m)
- ゆっくり転がるとちょっと傾いてるかも(3〜6mm/m)
- どんどん転がっていったら、かなり傾いています(6mm/m以上)
つまり、人が「ん?なんか斜めかも?」と感じる程度でも、実は6mm/mを超える傾きが出ていることもあります。
これを放っておくと、建物の構造部分が傷んでいたり、地盤が下がってきているケースもあるので注意が必要です。
◆ デジタル水平器の見方と使い方
デジタル水平器は、0.1度単位の傾きやmm/m(ミリパーメートル)での表示が可能で、床や柱の傾きを可視化できます。
代表的な表示モード:
- 【°(度)表示】:例)1.2° → かなり傾いている
- 【mm/m表示】:例)6.0mm/m → 水平1mで6mmの高低差
- 【%表示】:勾配の割合(外構や屋根でよく使います)
今回は「mm/m」で確認しており、目に見えないレベルでも沈みや傾きの傾向を数値で把握できるのが大きな利点です。
【調査事例】和室◆ 畳の劣化で正確に測れない?和室での測定の工夫
この物件では、床の傾きを調べるためにデジタル水平器を使用しました。
まず和室。ここでは畳が中央部分でかなり劣化しており、沈み込みが強かったため、正確な計測が難しい状態でした。
そのため、一箇所で判断するのではなく、部屋の四隅や縁側付近など複数箇所に分けて計測。
こうすることで、床の全体的な傾き傾向を把握することができました。
🛠 ポイント:
畳の上での測定は沈み込みによる誤差が出やすいため、畳の端や下地のしっかりした場所を選ぶのが基本です。
【調査事例】洋室◆ 床が“波打つ”ように沈む理由
洋室側では、畳の問題はないものの、床のあちこちで沈みや浮き上がりが見られ、波打ったような状態でした。
特に部屋の中央付近に顕著な沈み込みがあり、見た目では気づきにくいものの、歩いたときに足裏で違和感が出るような状態。
デジタル水平器で複数点をチェックすると、部屋の外周と比べて中央部分が4〜6mm沈んでいる箇所が確認できました。
◆ なぜ洋室の床が沈んだのか?間取りと構造が関係している可能性
今回注目すべきだったのは、沈みが出ていた洋室の下階が「和室」であり、真下に壁や間仕切りがほとんどない構造だったことです。
床の沈みは、直下に支持構造がない空間によく見られます。
特に築年数が経っている建物では、梁や根太のたわみや劣化も進行しており、構造的な“空白部分”が弱点となり、床が沈んでしまうケースがあります。
◆ 調査では「一箇所だけ」ではなく「全体を見て判断」
今回のようなケースでは、1~2箇所を計測しただけでは見落としてしまう情報もあります。
デジタル水平器を使い、部屋の複数ポイントを調べることが重要です。
📝 コツ:
部屋の対角線上や十字の位置関係で測ると、全体の傾向がつかみやすくなります。
床の傾きや沈みは、雨漏り・シロアリ・構造劣化のサインにもつながるため、慎重な判断が求められます。
◆ まとめ:床の“違和感”には理由がある
中古住宅を購入予定の方や、すでに所有している方も、「ちょっと床が斜め?」「歩くと沈む?」といった違和感に気づいたら、構造的な原因がないか一度 インスペクション を受けることをおすすめします。
床の傾きや沈みは、見た目だけでは判断できない構造リスクを教えてくれる重要なヒントです。