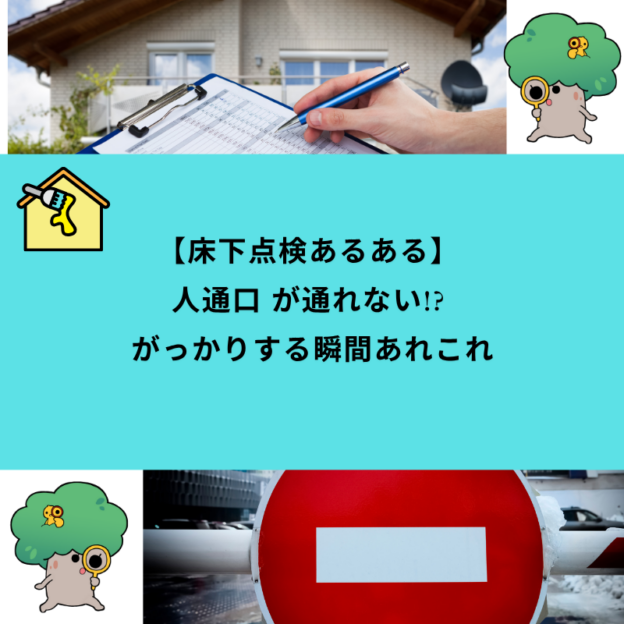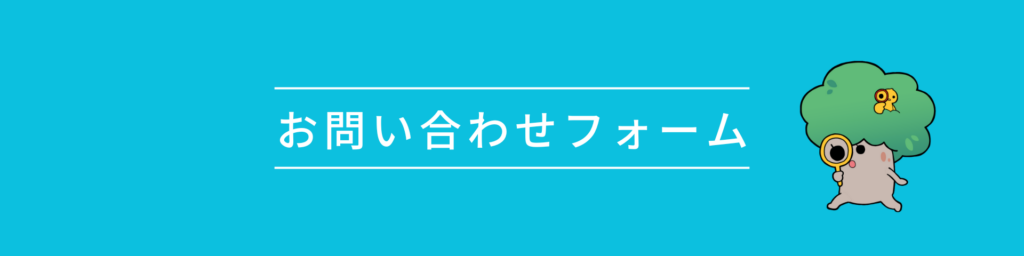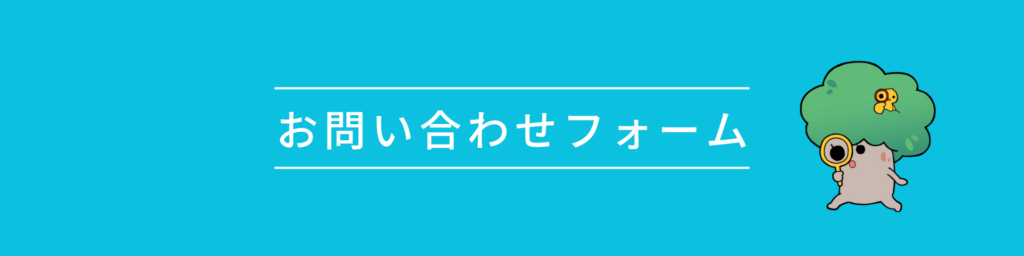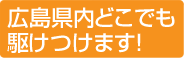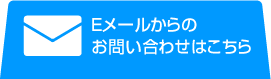建物の床下点検を行っていると、たまに「これは無理だ…」と頭を抱える瞬間があります。
今回は、人通口 が狭すぎたり、配管や束(つか)に塞がれて通れなかったりといった、
床下点検時の“あるあるがっかりシーン”を写真とともにご紹介します。
◆ 人通口 の真ん前にドン!と立ちはだかる配管

せっかく点検口を開けて、さあこれから床下へ!という時に、人通口 の真正面に太い配管が横たわっているケース。
これでは入るに入れず、どうしようもありません。
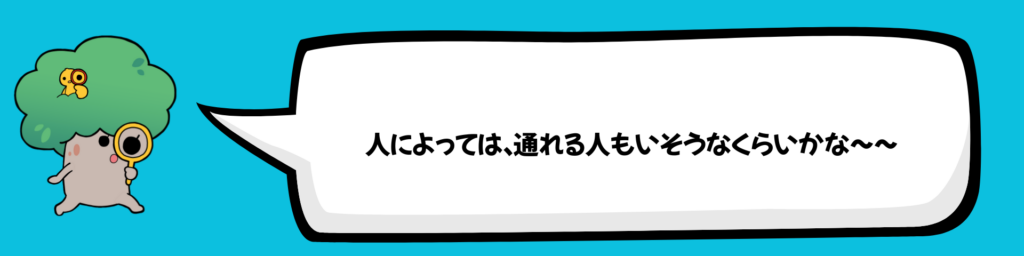
◆ 束が人通口 のど真ん中に…

本来人が通れるように確保されているはずの人通口 に、なぜか束が鎮座しているパターン。
作業の都合か…いずれにしても通れません。
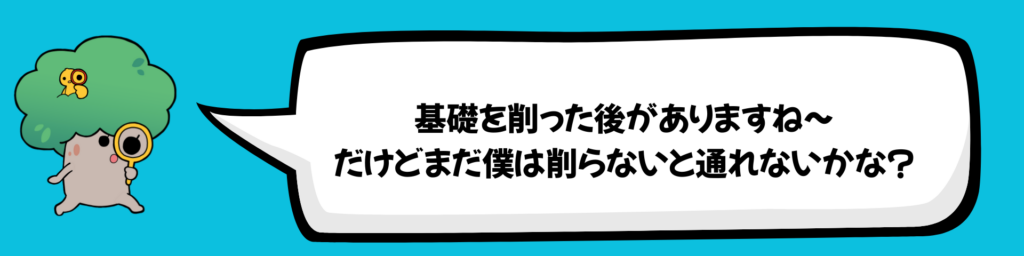
◆ 通れても、通った先が塞がれている…

中に入れても、奥に進めない。
配管や断熱材、時にはゴミなどで通路が完全に塞がれていることもあります。
調査や施工の目的地までたどり着けず、泣く泣く引き返すことに。
◆ 入れそうな気がして はいってみたら…

人通口の高さが、手をグッと広げて親指から小指までくらい。
「ん?これは…イケるかも?」と体をねじ込みながら入ってみたものの、思った以上にギリギリ。
中には入れたけど、今度は向きが変えられない。戻るにも一苦労。
最終的には、「なんでこんなところ通れたんだっけ…?」と軽くパニックに。
“通れる”と“通りやすい”は全然ちがう――そんなことを身をもって知る瞬間です。
◆ 床下は「人が入れる構造」も大事なチェックポイント
床下点検やシロアリ防除、断熱施工、配管のメンテナンスなどにおいて、人が安全に入れる構造であることはとても重要です。
新築・リフォーム問わず、設計段階で以下の点に注意が必要です:
- 人通口は450mm以上の幅を確保
- 人通口前に障害物(配管・束など)を配置しない
- 床下の通路を確保し、塞がない設計にする
- 点検・施工後も定期的に通れるか確認
◆ 点検できなければ「異常の早期発見」も難しい
床下の点検ができないと、シロアリ被害や漏水、湿気による木材腐朽などの“初期症状”を見逃してしまうリスクがあります。
定期点検が難しい構造のまま放置すると、将来的な補修費用が大きくなることも。
点検できる床下が、建物を守ります
床下は見えない場所ですが、点検や施工がスムーズに行える構造であることは非常に重要です。
人通口 の前に配管や束がある、通路が塞がれている――そんな状況では、必要な点検も十分に行えません。
人が通れる床下は、家を長く守るための基本。
設計や施工の段階で、少しの配慮が将来の安心につながります。
よくある質問
Q1. 人通口の標準サイズはどれくらいですか?
A. 一般的には幅450mm以上が推奨されています。これにより、点検や施工時に人が安全に通れるスペースを確保できます。
Q2. 人通口が狭い場合、どうすればいいですか?
A. 既存住宅の場合は、基礎を一部削るなどの改修が必要になることがあります。ただし、構造に影響を与えないよう専門業者に相談してください。
Q3. 床下点検はどれくらいの頻度で行うべきですか?
A. シロアリ防除や漏水チェックのため、少なくとも5年ごと、または防蟻保証の更新時に行うのが理想です。
Q4. 床下に入れない場合、点検はどうするの?
A. 床下カメラや内視鏡を使った調査が可能ですが、全体を確認するには限界があります。構造的に人が入れる状態にしておくことが重要です。
Q5. 新築時に注意すべきポイントは?
A. 人通口のサイズ確保、障害物の配置を避ける、通路を塞がない設計が基本です。設計段階で施工業者に確認しましょう。