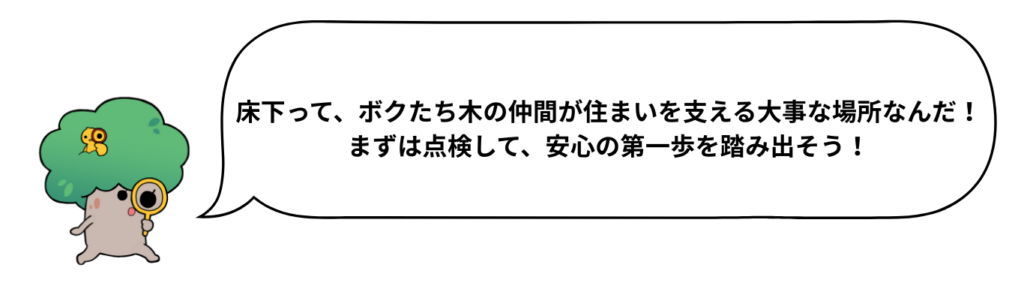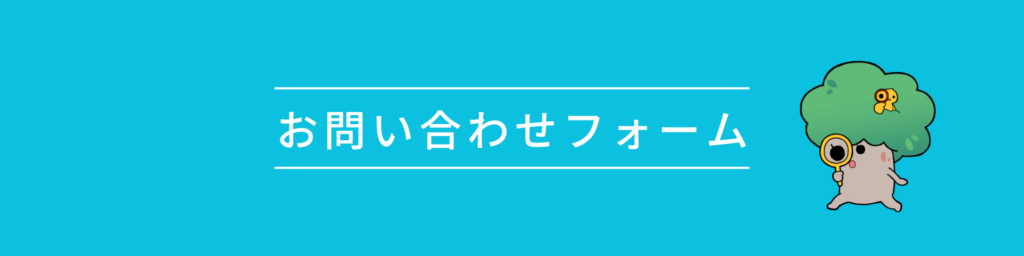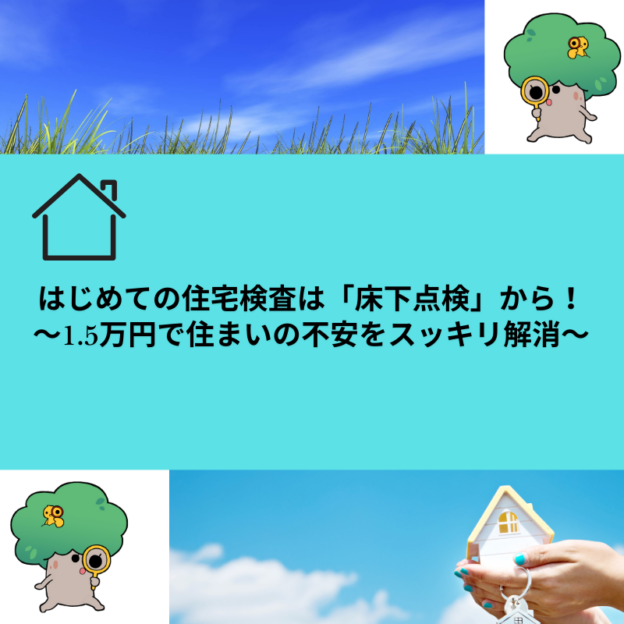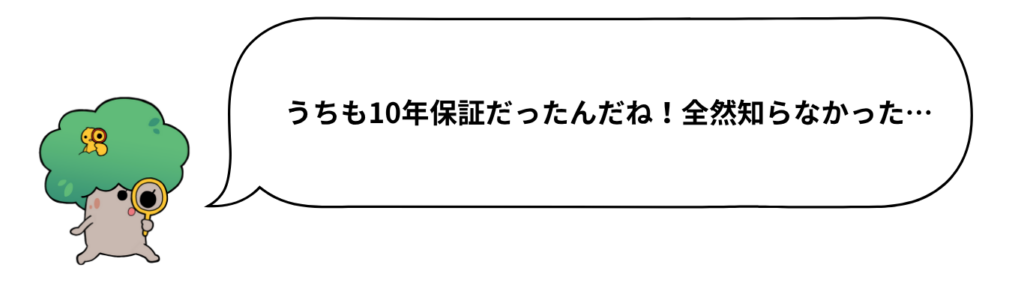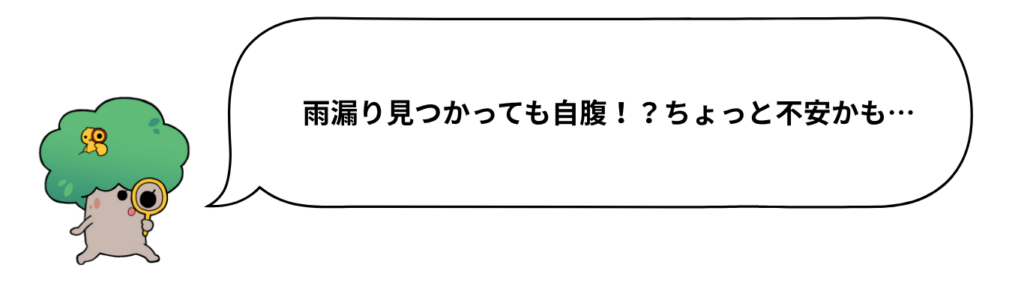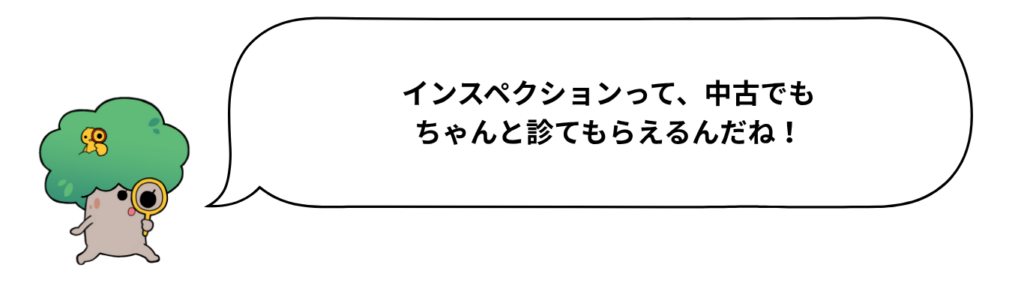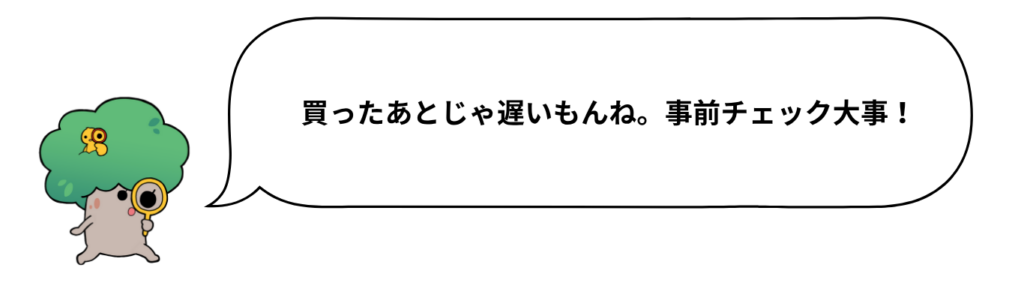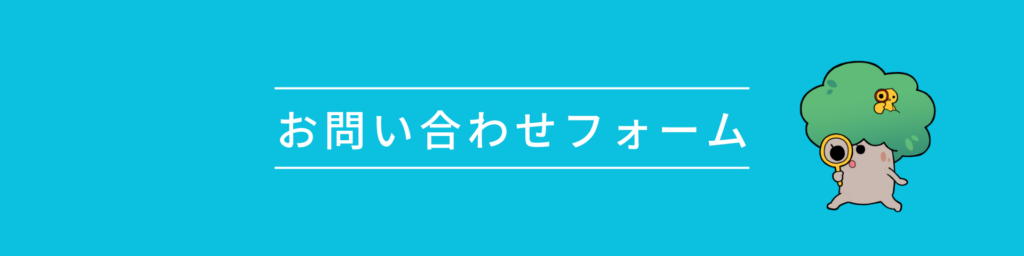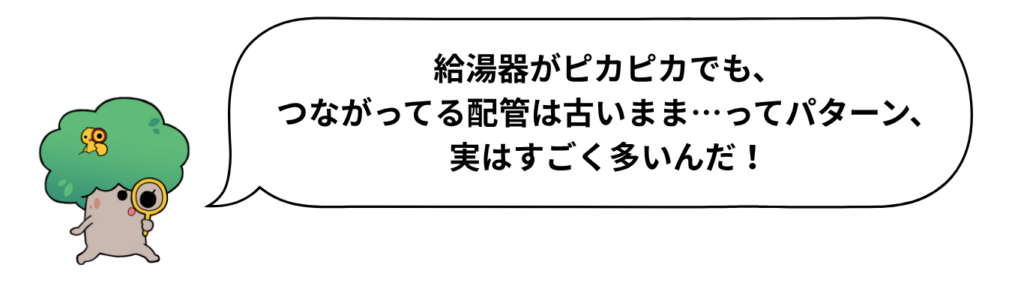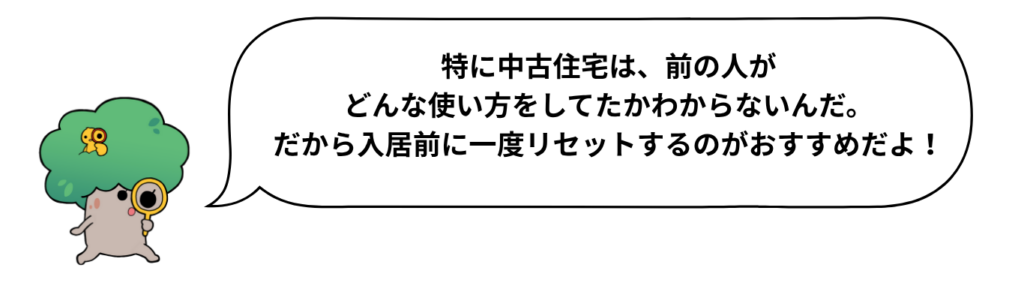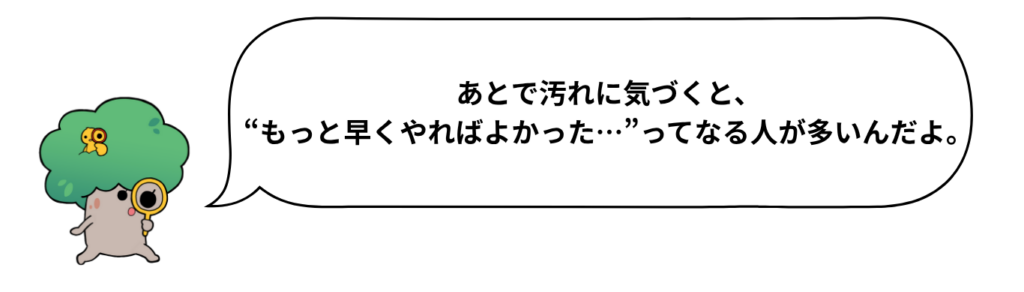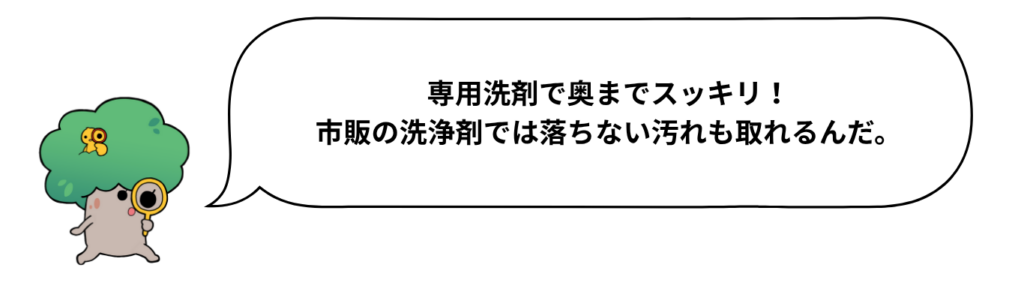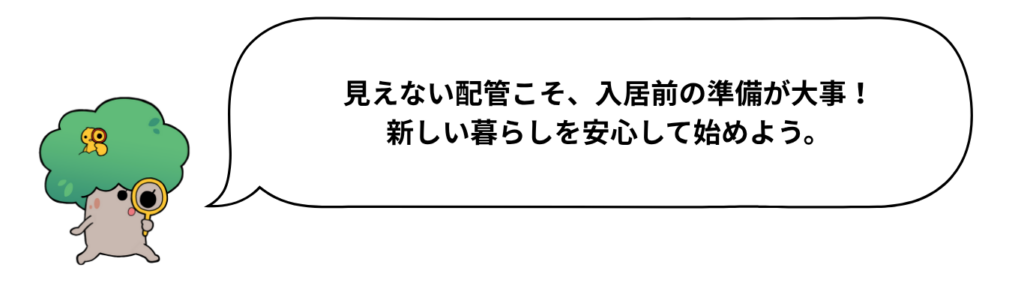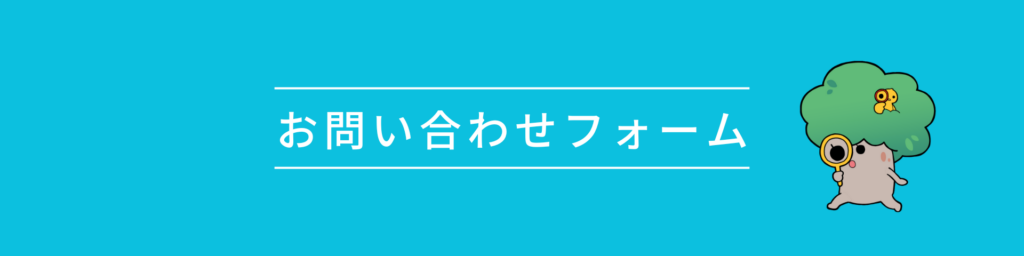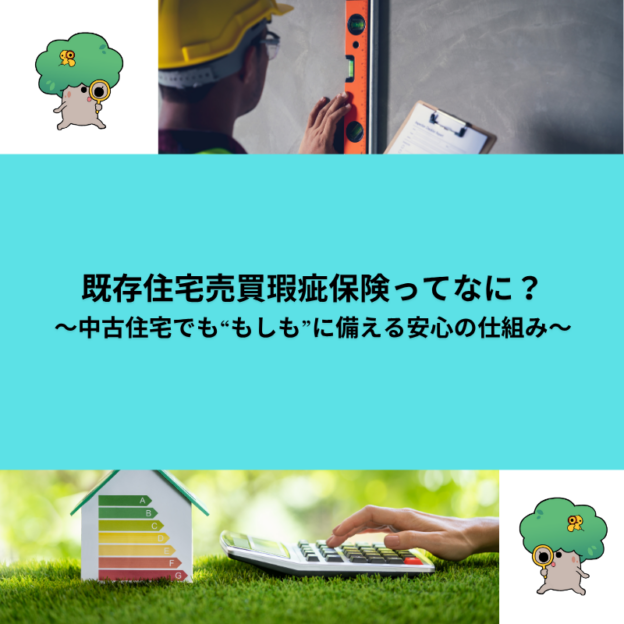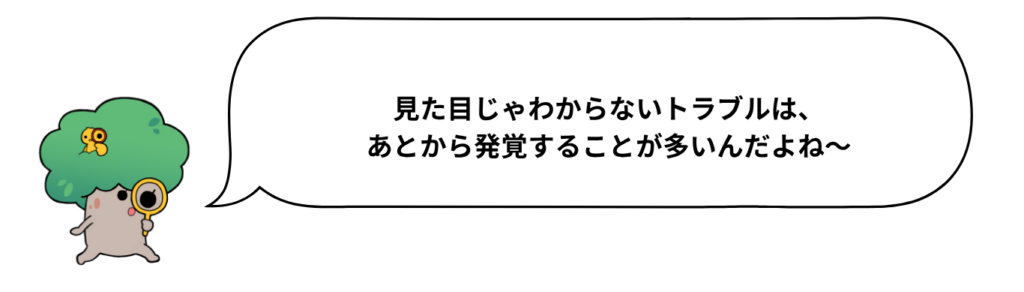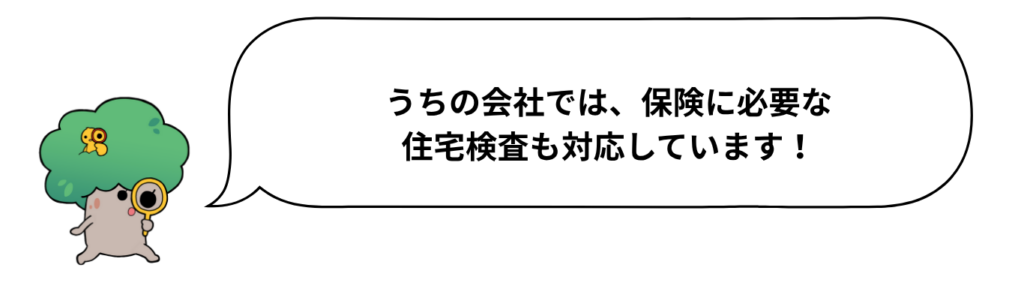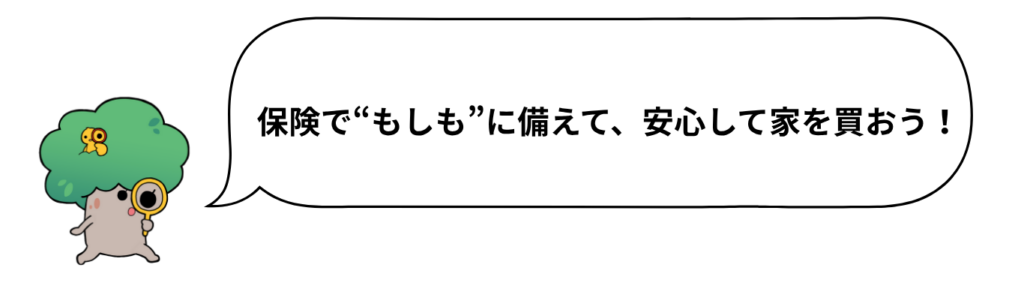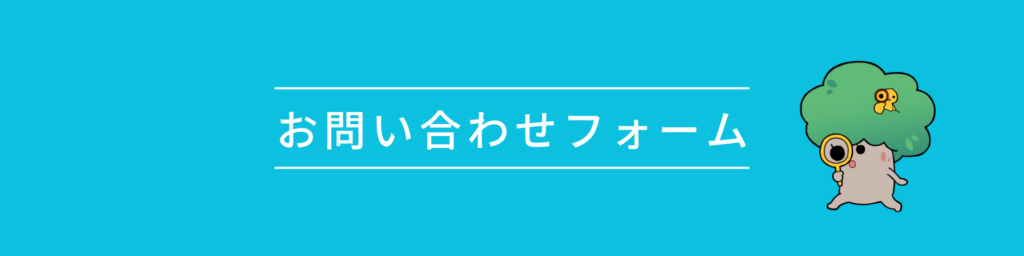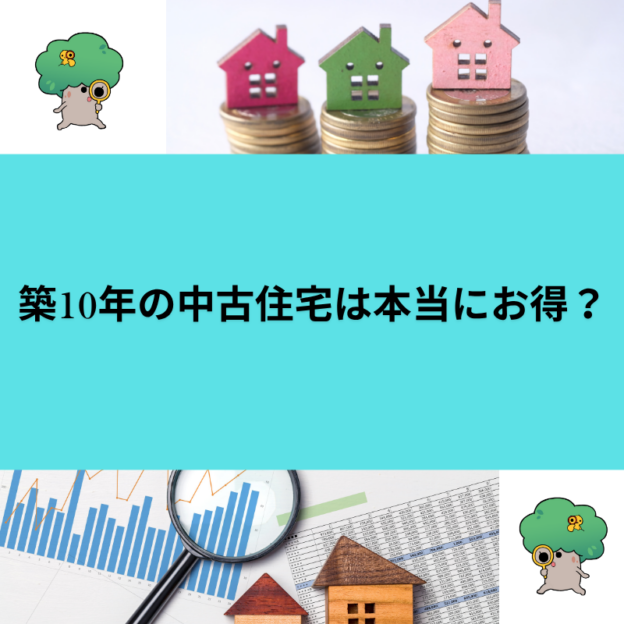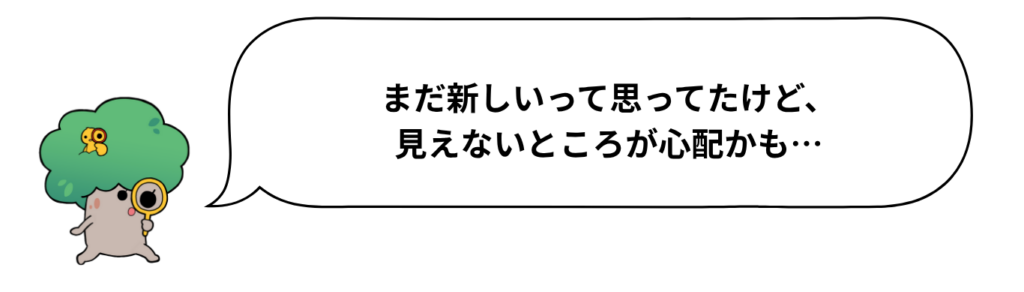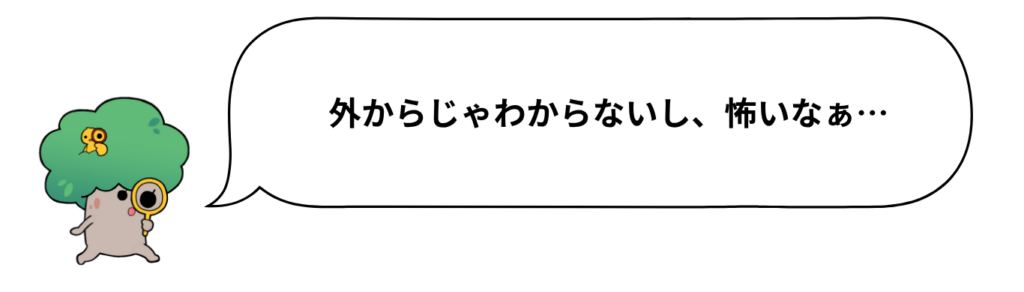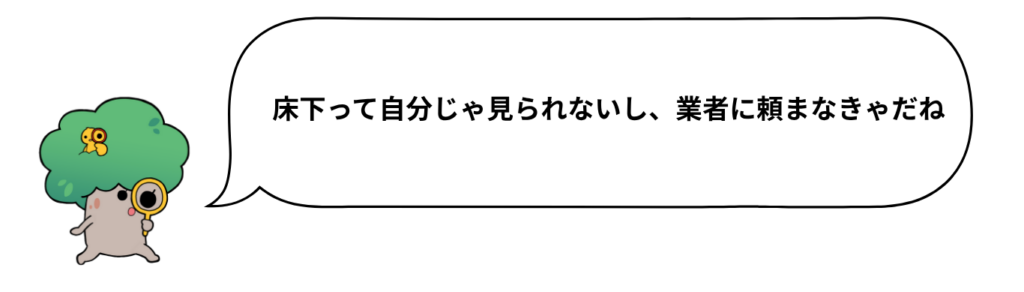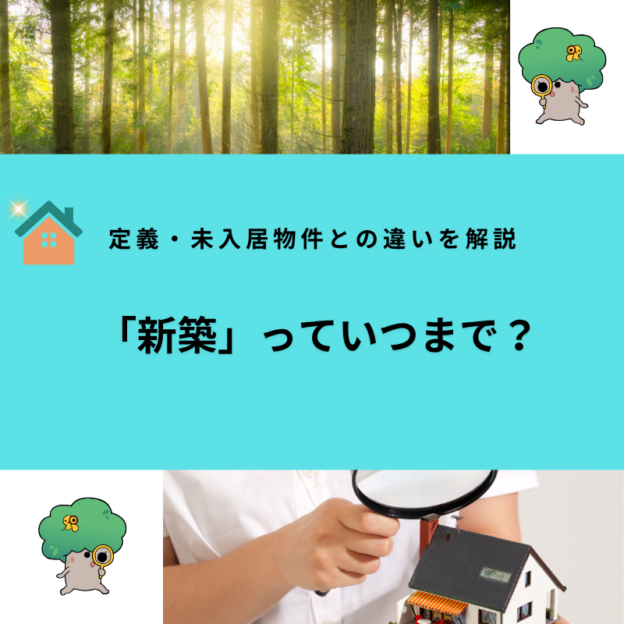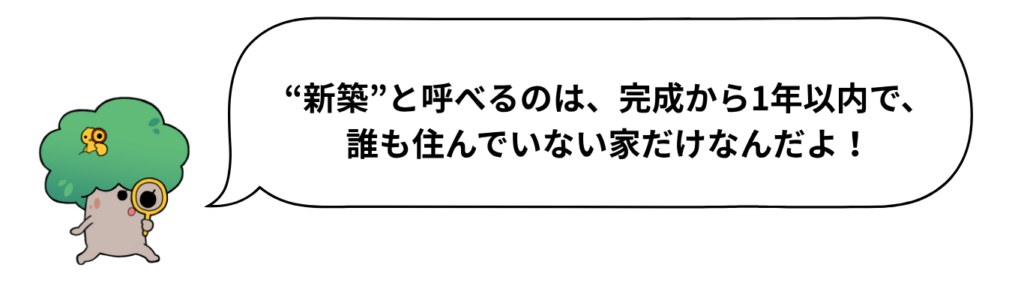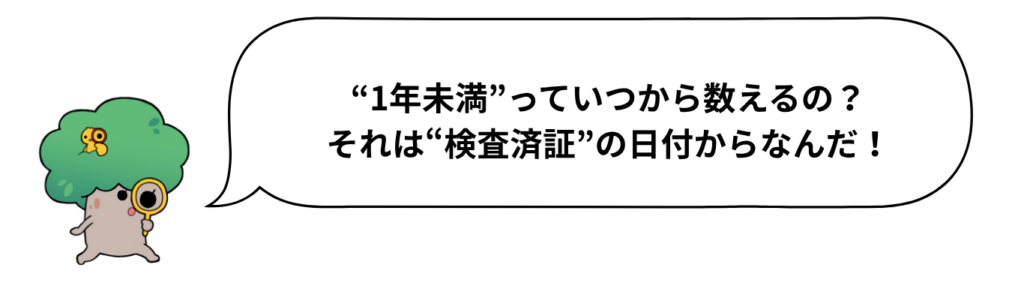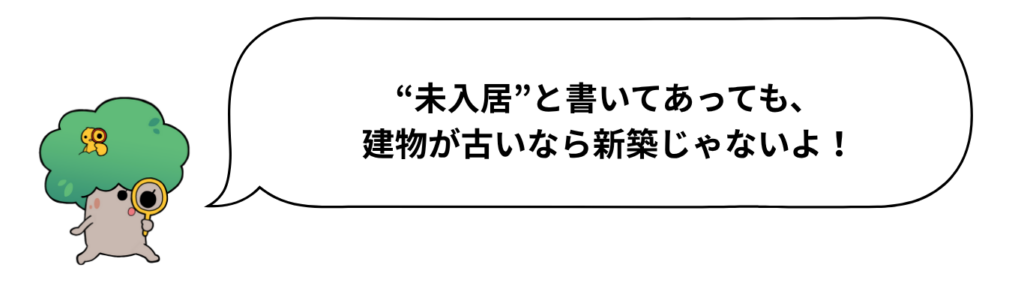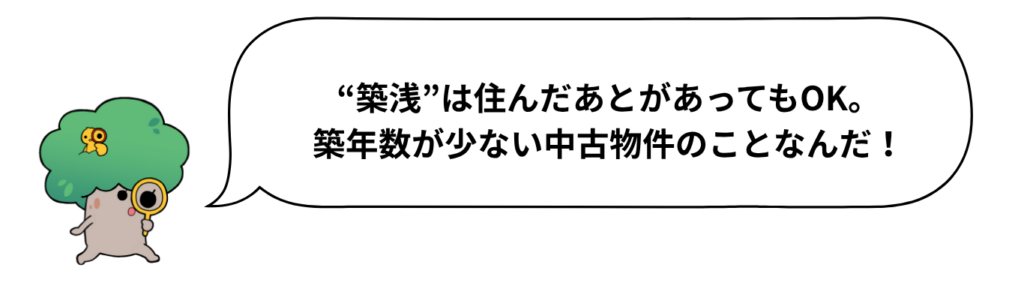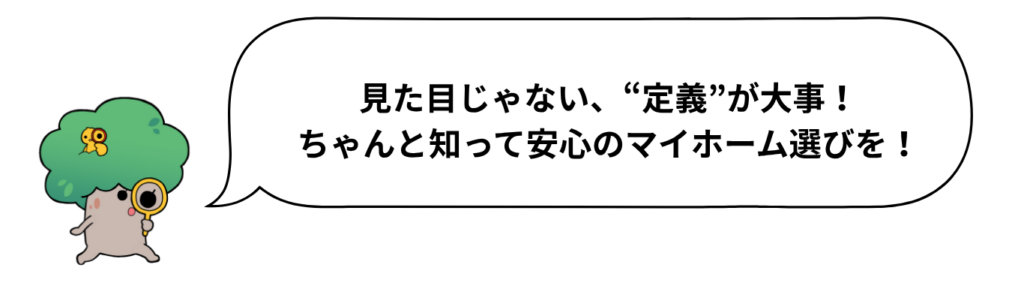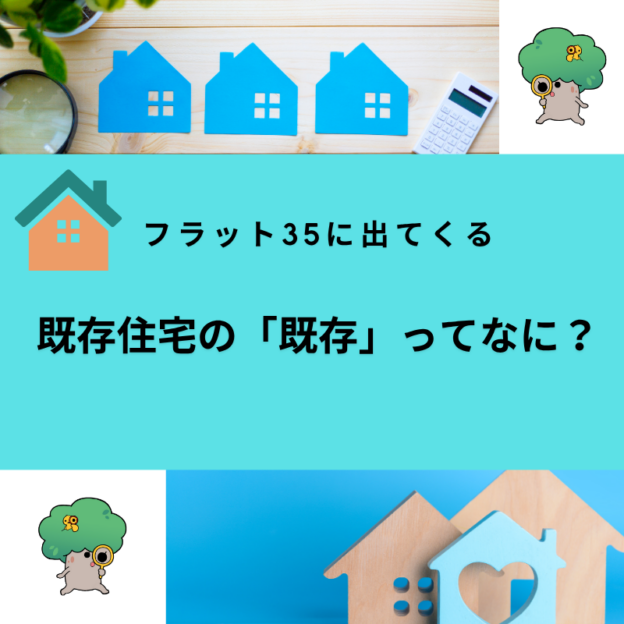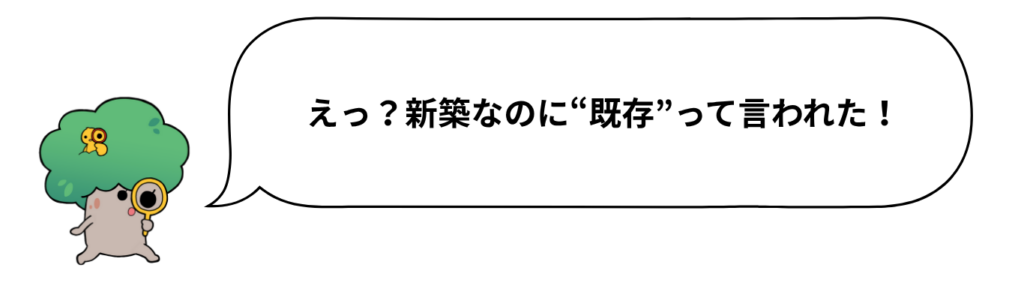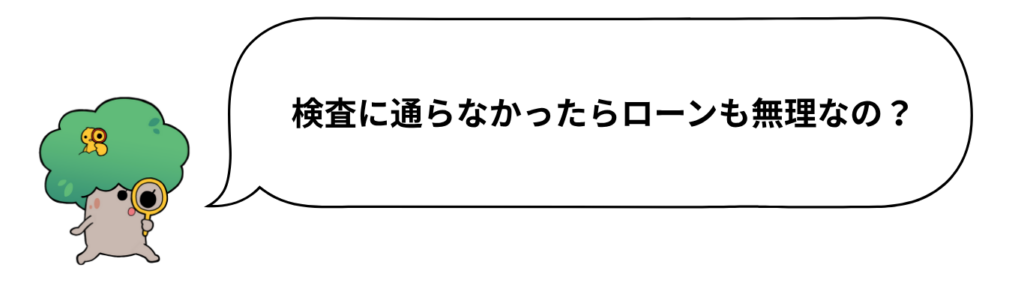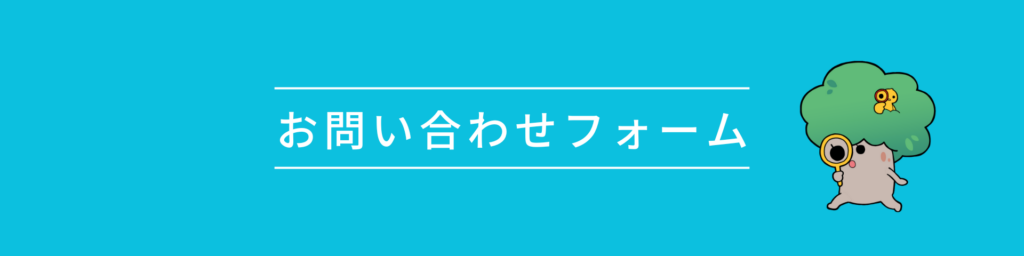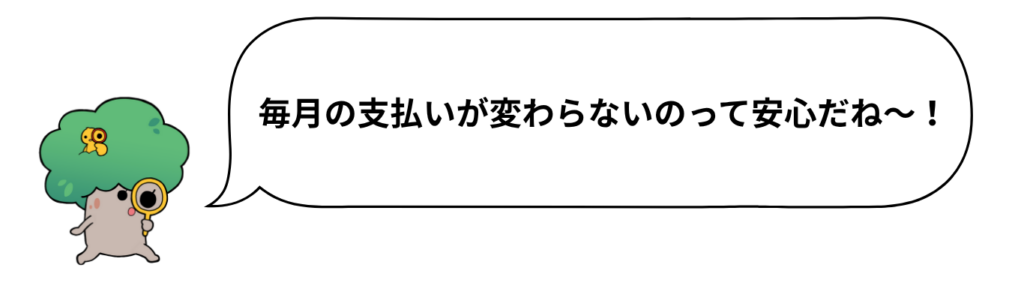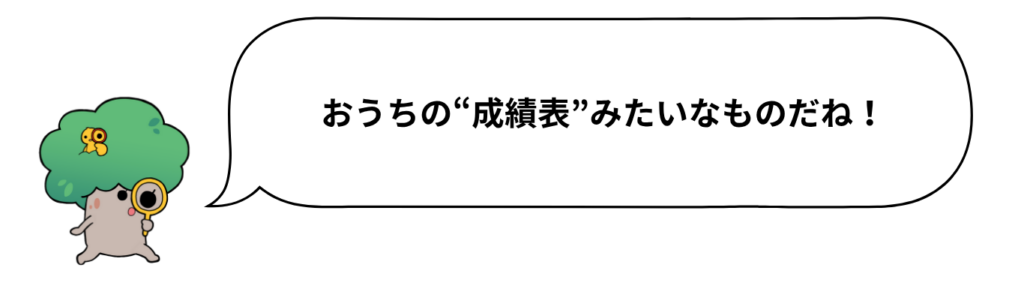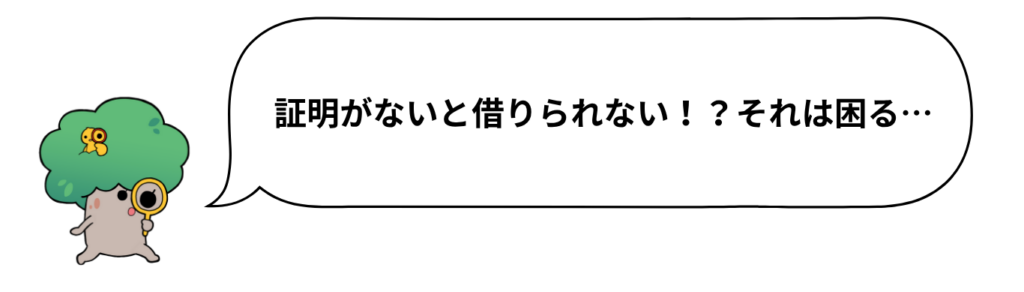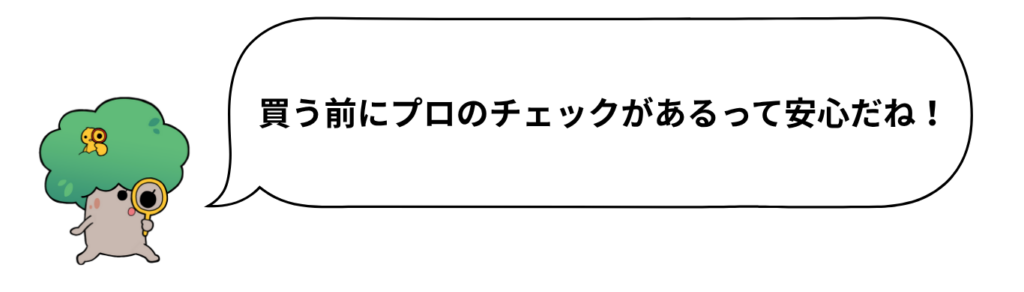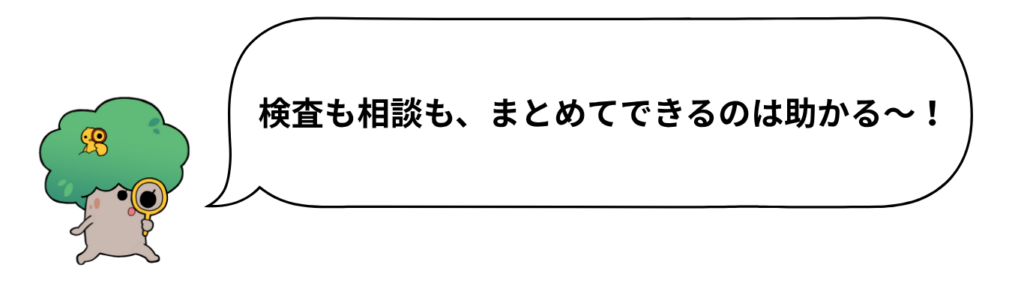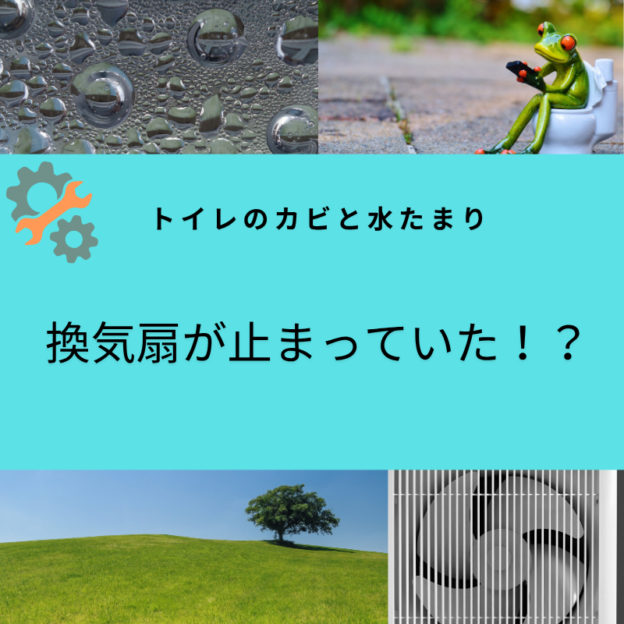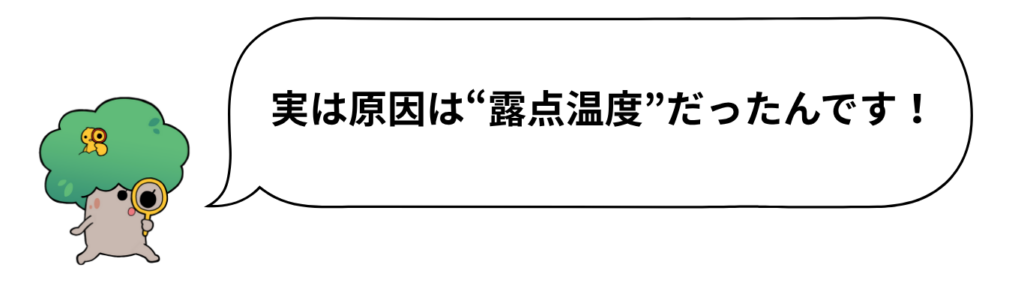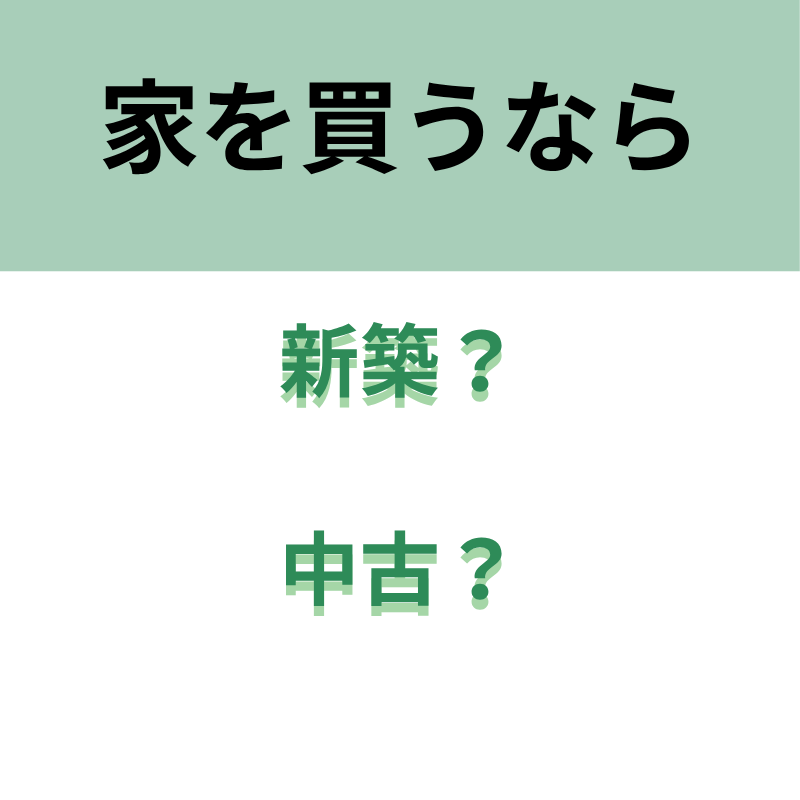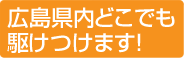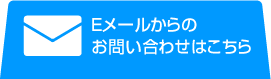中古住宅を買ってリノベーションする人が増えています。快適で安心、しかも自分らしい住まいづくりのポイントをやさしく解説!
「家を買うなら新築」は、もう昔の話?
これまで日本では「家を買うなら新築でしょ」という考え方が当たり前でした。
中古の家は“仕方なく選ぶもの”と思われていた時代もあります。
でも今は時代が大きく変わりました。
家を建てるための費用がどんどん上がり、職人さんの数も減っている今、新築を買える人は限られてきています。
その一方で、すでにある家を買って、自分たちの暮らしに合わせて直して住む「中古住宅+リノベーション」という選び方が、現実的で満足度の高い方法として注目されています。
実は、中古でも「しっかりした家」はたくさんある
築30年の家と聞くと「古い家」と思うかもしれませんが、1995年以降に建てられた家は、地震に強い基準で造られたものが多く、しっかりした造りの家も少なくありません。
特に2000年代前半の家は、今の家よりも丁寧につくられているものも多く、中古とはいえ、状態が良い物件も意外とたくさんあります。
住宅ケンコウ社では、家を買う前に“見えないところ”まで調べる「住宅診断(ホームインスペクション)」を行っていますが、その中で「まだまだ長く住めるいい家」と出会うこともよくあります。
「直して住む」から得られる満足感|リノベーションの満足度が高い理由とは?
実際に、中古住宅を購入して自分たちでリノベーションした人たちは、住まいへの満足度が非常に高いという調査結果があります。
中には、新築の注文住宅よりも満足度が高いという結果も出ています。
出典:マイナビニュース(2023年2月)
リノベーションでは、間取りや内装を自分たちの暮らし方に合わせて考えることができます。
たとえば、こんな希望もリノベーションなら叶えられます。
- リビングを広くしたい
- 子ども部屋を将来仕切れるようにしておきたい
- ペットに優しい素材を使いたい
そんな希望をカタチにしていくことで、「本当に住みやすい家」がつくれます。完成したときの喜びはもちろん、そのプロセスが家への愛着を深めてくれるのです。
中古住宅を買うときは、まず「状態チェック」が大事
家を買ってから「こんなところが壊れてたなんて…」と後悔したくないですよね。
そこでおすすめなのが、プロによる「住宅診断(ホームインスペクション)」です。
これは、建物のゆがみ、雨漏り、シロアリなどの被害、設備の老朽化など、家の状態を事前に調べておくものです。
中古マンションの場合は、自分の部屋(専有部分)だけでなく、廊下やエレベーターなどの共用スペースの管理状況や修理の計画も確認しておくと安心です。
2025年からは「省エネ(エネルギー効率の良さ)」がルールに
2025年4月から、「リフォームや増改築をする場合にも、省エネ性能が一定の基準を満たす必要がある」というルールが始まりました。
簡単に言えば「暑さ・寒さに強い家にしましょう」という話。
たとえば、
- 窓を断熱性の高いものに変える
- 壁や床に断熱材を入れる
- 省エネのエアコンや給湯器を使う
などの工事が求められるようになります。
さらに2030年には、その基準がさらに厳しくなっていく予定です。
リフォーム会社は「選び方」が重要に
こういった新しいルールに対応するには、知識のあるリフォーム会社を選ぶことがとても大切です。
家の中を快適にするには、断熱や空気の流れ、水まわりの構造など、細かい計算や工事が必要です。
住宅ケンコウ社では、
- 家の状態を調べる「住宅診断」
- 補助金の活用方法のご案内
- 実際の施工までワンストップで対応
など、お客様にとってわかりやすく、安心できるサポートを心がけています。
知っておきたい!お得な補助金制度
リフォームや省エネ工事に対しては、国や自治体から「補助金」が出ることもあります。
たとえば、「子育てエコホーム支援事業」という制度では、断熱工事や省エネ設備の設置などを行うと、最大60万円の補助が出る場合もあります。
「子育て」と書いてあっても、対象になるのは子育て世帯だけではなく、一般のご家庭でも利用できる制度です。
住宅ケンコウ社では、こうした補助金の情報も丁寧にお伝えし、申請サポートも行っています。
少しだけでも「自分で手を加える楽しさ」
「リノベーション」と聞くと、すべて業者に頼まないといけないように感じるかもしれませんが、ちょっとした部分だけ自分でやってみるのもおすすめです。
たとえば、
- 壁に好きな色を塗る
- 壁紙を貼り替えてみる
- 棚をつくってみる
そんなDIY的な工夫でも、家に対する愛着はぐっと増します。
今後は職人さんが減っていくこともあり、「ちょっとした修理は自分でできる」というスキルも、ますます大切になるかもしれません。
家を「育てる」という考え方
中古住宅+リノベーションは、「今ある家を活かして、自分たちの理想に近づけていく」という考え方です。
新築より費用を抑えつつ、快適さや住み心地、そして自分らしさを手に入れることができます。
そしてなにより、これからの時代に求められる「環境への配慮」や「家を長く大切に使う」という社会全体の流れにも合った住まい方です。
住宅ケンコウ社では、家を「買う前」から「住み始めた後」まで、一人ひとりのご家族に寄り添ったサポートを行っています。
「安心して暮らせる家」「長く住み続けられる家」を一緒に探し、つくっていきませんか?